茨城県交通安全協会主催による「茨城弁交通安全川柳コンテスト」というものがありました。
茨城弁を誇りに思っている人が発案したのか、それとも自虐ネタ的な意味合いがあるのかは分かりませんが、入賞作品を見ると、茨城弁というのは七五調の川柳になかなかマッチするようです。
茨城県の国道を走っていると、こうした茨城弁の川柳が描かれたノボリがはためいているのを見かけることがあります。
確かに茨城弁を理解することのできるネイティブの茨城県民であれば、こうしたノボリを見ることでほっこりとすることでしょう。
しかし、国道を走っているのは茨城県民ばかりではありませんし、茨城県に生まれ育った人であっても若い人などはまったく茨城弁が分からない人も増えています。
はたしてこのノボリの効果がどれくらいあるのかは、分からないですね。
ここでは、第1回と第2回の「茨城弁交通安全川柳コンテスト」の入賞作を紹介すると同時に、標準語に翻訳してみたいと思います。
第1回茨城弁交通安全川柳入賞作品
平成18年に実施された第1回茨城弁交通安全川柳コンテストの入賞作品の中から、いくつかの句を紹介してみたいと思います。
運転者部門
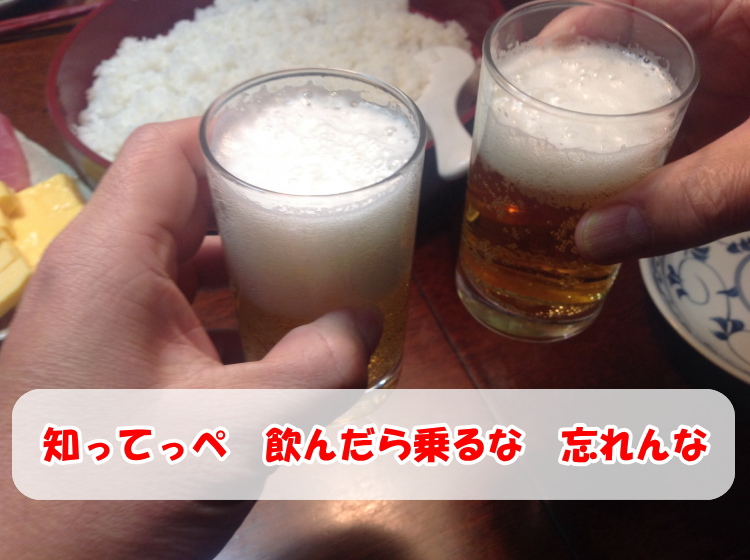
運転者部門の最優秀作品は次の句になります。
『知ってっぺ 飲んだら乗るな 忘れんな』
こちらは水戸市の會沢盛三郎さんの作品です。
この句を標準語に翻訳しますと「知ってるよね?飲んだら乗るなを忘れんなよ」といったニュアンスになるかと思います。
飲酒運転をしてはいけないのは、ドライバーであれば常識中の常識です。
それを「知ってっぺ」という表現で強調しているわけですね。
次の句は優秀賞になります。
『ウインカー 早めに出さなきゃ ダメだっぺ』
こちらは、茨城町の武田直之さんの作品です。
茨城弁を知らない人でもなんとなく意味は分かると思いますが、念のために翻訳をすると「ウインカーは早めに出さないとダメだよ」という意味になります。
確かに、曲がる直前にウインカーを出す人が多いですね。
次も優秀賞になります。作者は茨城町の高野智充さんです。
『締めっぺよ シートベルトは 命綱』
標準語になおすと「締めようぜ、命ベルトは命綱だから」となります。
交通事故の死亡者数は45年前の4分の1にまで減っているようですが、やはりシートベルトを締めるようになったことが大きな要因の1つになっていると思われいます。
参考:交通事故の死亡者数が45年前の4分の1にまで減った理由とは?
高齢者部門

高齢者部門の入賞作品を紹介します。
まずは最優秀賞になります。作者は水戸市の関富喜子さんです。
『着けっぺよ くつや帽子に 光るもの』
翻訳すると「つけましょう、くつや帽子に光るものを」ということになります。
やはり茨城弁らしく、どの作品にも「ぺ」が用いられていますね。
次は優秀賞で、日立市の関光枝さんの作品です。
『よかっぺと 無茶な横断 怪我のもと』
翻訳しますと「大丈夫だろうと無茶な横断をすると怪我しますよ」となります。
無茶な横断は怪我どころか、命にかかわるので絶対にやめた方がいいですね。
次も優秀作で、水戸市の加地由有子さんの作品です。
『見せっぺよ 紅葉マークで 良い手本』
標準語に翻訳しますと、「見せましょうよ、紅葉マークで良い手本を」となります。
紅葉マークというのは高齢者がクルマに取り付けるシルバーマークのことですが、現在では紅葉マークではなくて、クローバーのマークになっていますね。
歩行者・自転車部門
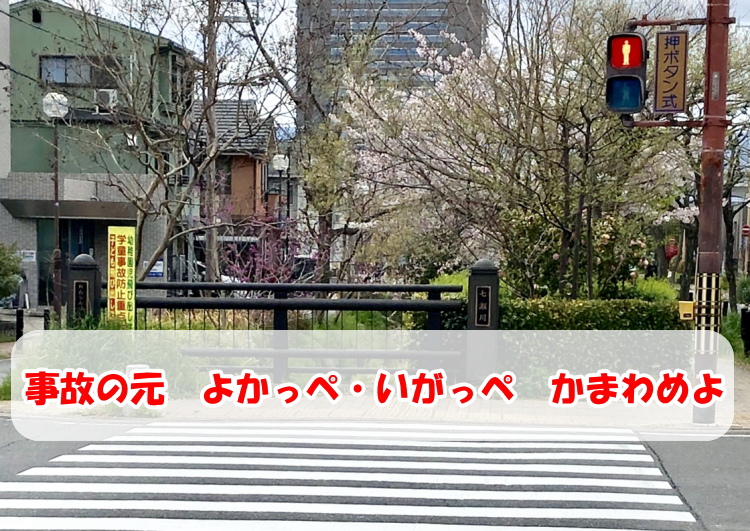
歩行者・自転車部門の入賞作品を紹介します。
最優秀賞は日立市の村上勝雄による次の作品です。
『事故の元 よかっぺ・いがっぺ かまわめよ』
茨城弁をこれでもかというほど詰め込んだ作品で「大丈夫だろうという考えが事故の元だよ」という意味になります。
「よかっぺ」も「いがっぺ」も「かまわめよ」もみんな似たような意味で、「大丈夫だろう」というニュアンスになります。
次は優秀賞で、常陸太田市の斎藤松雄さんの作品です。
『信号を 親が無視しちゃ ダメだっぺ』
翻訳すると「信号を親が無視しちゃだめでしょう?子どもがマネするよ」といった意味になります。
確かに、歩行者用の信号が赤なのに、クルマが来ないのをいいことに子どもと一生に横断してしまう親がときどきいますね。
子どもは親を見て育ちますので、子どもの前で悪い見本を示すのは絶対にやめてもらいたいですね。
次も優秀賞で、作者は日立市の小松弘二さんです。
『自転車も ルール守らにゃ だめだっぺ』
意味は「自転車もルールを守らなくちゃだめだよ」になります。
自転車は、道路交通法上は軽車両にあたりますが、違反してもクルマやバイクのように罰則がないために、ルールを守らない人が多いですね。
第2回茨城弁交通安全川柳入賞作品
平成19年に行われた、第2回茨城弁交通安全川柳コンテストの入賞作品を紹介します。
第1回では、運転者部門、高齢者部門、歩行者・自転車部門の3部門となっていましたが、第2回では、飲酒運転部門、シートベルト部門、反射材部門の3部門に変わっています。
飲酒運転部門

まずは、飲酒運転部門の最優秀賞の紹介です。こちらの作品は、古河市の初見隆則さんの句です。
『知ってっか 飲ませたおめえも 共犯者』
意味は「知ってるか?飲ませたお前も共犯者だぞ」になります。
飲酒運転は、クルマを運転する本人だけではなく、クルマに乗って帰るのを知っていながら飲ませた方も罰せられることになります。
「知ってっか」と問いかけていますが、意外に知らない人が多いのでしょう。
次は優秀賞で、鉾田市の新堀浩子さんの作品になります。
『飲んで乗る そおた話は あんめえよ』
標準語に変換しますと「飲んで乗るなんて、そんなことは許されませんよ」ということになります。
標準語だときつい表現に感じることばも、茨城弁だと少しあたりが柔らかくなるような気がしますね。
次も同じく優秀賞になります。作者は茨城町の山口祐子さんです。
『決めとくべ 飲んでいい人 悪い人』
意味は「決めておきましょう、飲んでいい人と悪い人を」になります。
クルマに乗って帰るのならば、誰が運転するのかを最初から決めておくことは大切ですね。
シートベルト部門

シートベルト部門の入賞作品の紹介です。
最優秀賞は、那珂市の野内幸枝さんによる次の作品です。
『つけっぺよ 乗ったらベルト 締める癖』
翻訳しますと「クルマに乗ったらシートベルトをつけましょう。締める癖をつけましょう」ということになります。
「つけっぺよ」が、「乗ったらベルト」と「締める癖」の両方にかかっているのが見事ですね。
次は優秀賞で、那珂市の海野寿子さんの句になります。
『前の席 後ろの席も 締めっぺね』
意味は「前の席だけではなく後ろの席もシートベルトを締めましょう」になります。
前の席に乗るときにはほとんどの人がシートベルトを締めていますが、残念ながら後ろの席に乗るときには忘れてしまう人が多いようです。
こちらも同じく優秀賞で、稲敷市の田村ゆき恵さんの作品です。
『乗せねえど ベルト締めない ごじゃっぺは』
標準語に翻訳すると「シートベルトを締めないアホは乗せてあげないよ」になります。
茨城県の代表的な方言である「ごじゃっぺ」がとうとう出てきましたね。
反射材部門

第2回茨城弁交通安全川柳の反射材部門の入賞作品を紹介します。
最優秀作品は、鉾田市の清宮努さんによる次の作品になります。
『付けてっぺ 小さなお守り 反射材』
意味は「付けていますよね?小さなお守りである反射材を」になります。
「ぺ」も使い方によって意味が変わるのですが、この句の「付けてっぺ」のように語尾をあげて発音するときには、相手に問いかけをする感じのニュアンスになります。
次は優秀賞で、那珂市の飯塚進市さんの作品です。
『ばんかだは ひかるタスキで でがけっぺ』
ちょっと難易度の高い茨城弁が使われているので、ネイティブ以外の方はピンと来ないかも知れませんが「夕方は、光るタスキをつけて出かけましょう」という意味になります。
「ばんかだ」を夕方と翻訳できる人は、かなり本格的な茨城の土着民だと思います。
次も優秀賞になります。作者は那珂市の高岡朋子さんです。
『暗い道 光っぺ見えっぺ 反射材』
意味は「暗い道で反射材をつけると光ってよく見えるでしょう」になります。
「光っぺ見えっぺ」と「ぺ」を連続して使っていてなんともゴロがいいですね。
他の回の俳句をご覧になりたい方は、以下のリンク先より1回~10回分全部をご覧になれますので、どっぶり茨城弁の交通安全俳句に浸ってみてください。
参考:【第1~第10回】茨城弁交通安全川柳コンテスト入賞作品
文:護持八平

